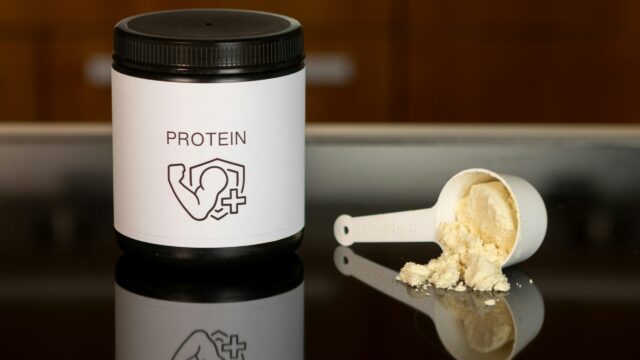筋トレで同じ部位をやっていい頻度は?理想の頻度とトレーニング法を徹底解説


「同じ部位の筋トレってどのくらいの頻度でやっていいんだろう?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
「毎日鍛えたほうが早く筋肉がつく?」
「間隔を空けすぎると意味がない?」
と、正解が分からず悩んだまま同じ部位の筋トレをしている人も多いと思います。
結論から言うと、筋トレで同じ部位を鍛える理想の頻度は、筋トレをする目的によって変わります。
がむしゃらに同じ部位の筋トレの回数を増やすだけでは、成果が出なかったり、回復が追いつかず逆効果になることがあります。
今回は、筋トレで同じ部位を鍛える理想の頻度の目安や、筋肥大・筋力アップを目指す人におすすめのトレーニング方法を、筋トレ初心者にも分かりやすく解説します。
本記事を読めば、自分に合った「同じ部位を鍛える理想の頻度」が分かり、
無駄なく効率的に筋トレを続けられるようになるので、ぜひ参考にしてみてください!
目的別|筋トレで同じ部位を鍛える理想の頻度とは?


①:筋肥大が目的の場合の頻度
筋肥大が目的の場合は、同じ部位を週2〜3回程度鍛えるのが理想の頻度です。
筋トレはやった分だけ効果が出ると思われがちですが、実際は休息中に筋肉が成長するという仕組みです。
トレーニングで筋肉に微細なダメージが生じ、それが修復される過程で強く太くなります。

なので、筋肥大が目的の場合は同じ部位を連日鍛えないよう注意することが大切です。
目安として、部位ごとに48〜72時間の回復期間を設けると良いでしょう。
休むことも「筋トレの一部」と考え、無理なく継続できるリズムを作りましょう。
頻度にこだわることも大切ですが、「回復できているか」も意識することが筋肥大を成功させる大事なポイントです。

②:筋力アップが目的の場合の頻度
筋力アップを目的に筋トレを行う場合も、同じ部位を週2〜3回程度鍛えるのが理想の頻度です。
筋力アップは筋肥大よりも神経系の回復が重要になるので、筋肉への刺激と休養のバランスを取ることが欠かせません。
高重量を扱うトレーニングでは、筋肉だけでなく関節や腱への負担も大きくなります。
なので、毎日同じ部位を鍛えるよりも、十分な回復時間を確保したほうが、結果的に重量の伸びにつながりやすくなります。
筋力アップを狙う場合の筋トレのポイントは以下の3点。
- 1セットあたり3〜6回
- 高重量を扱う
- セット間の休憩を長めに取る
といったトレーニングが中心になります。
筋力アップでは「どれだけ回復できているか」が成果を左右します。
疲労が残っていると感じた際は、無理に筋トレをしようとせず、休養を優先することも大切です。
③:ダイエットが目的の場合の頻度
ダイエットを目的に筋トレを行う場合も、同じ部位は週2〜3回程度鍛えるのが理想の頻度です。
脂肪を落とすためには消費カロリーを増やすことも重要ですが、リバウンドしないために筋肉量を向上させることも欠かせません。
回復を挟みながら、定期的に筋肉へ刺激を与えることが、ダイエット成功のポイントです。
ダイエットが目的の場合の筋トレのポイントは以下の3点。
- 1セットあたり10〜15回
- いつもより少し軽めの重量を扱う
- インターバルを短めに
といった意識で行うと、消費カロリーを高めやすくなります。
また、ダイエットが目的の場合は、同じ部位を鍛える頻度だけでなく、全身をバランスよく鍛えることも重要です。
有酸素運動を筋トレ後にやるのも、脂肪燃焼効果をさらに高めることができます。

筋トレで同じ部位を効率よく鍛えるために知りたいポイント
全身法と分割法の違いと選び方
筋トレで同じ部位を鍛える頻度を考える前に、全身法と分割法の違いを理解しておくことはとても重要です。
結論、「どちらが正解か」ではなく、目的やライフスタイルによって向き・不向きがあります。
全身法とは、1回の筋トレで全身の筋肉をまんべんなく鍛える方法です。
週2〜3回の筋トレでも、同じ部位に定期的に刺激を入れられるため、筋トレ初心者や忙しくて頻繁にジムへ行けない人に向いています。
これに対して分割法は、日ごとに鍛える部位を分けるトレーニング方法です。
例えば「胸・腕の日」「背中・脚の日」といった形で分けることで、1部位あたりのボリュームを増やしやすくなります。

選び方のポイントは、
- 筋トレができる頻度
- 筋トレの目的(筋肥大・筋力アップ・ダイエット)
- 回復にかけられる時間
を基準に考えることです。
週に2〜3回しか時間が取れない場合は全身法、週4回以上トレーニングできるなら分割法といったように、無理なく続けられる方法を選ぶことが大切です。
頻度だけにこだわらず、自分の生活リズムに合ったトレーニング法を選ぶことで、長期的に成果を出しやすくなります。
1週間単位の筋トレの組み方と頻度の調整
筋トレで同じ部位を効果的に鍛えるためには、1週間単位の筋トレの組み方と頻度の調整がとても重要です。
やみくもにトレーニングするのではなく、回復を考慮した計画を立てることで、効率よく成果を出しやすくなります。
とにかく意識したいのは、同じ部位に連続して強い負荷をかけないこと!

なので最低でも1〜2日の休養を挟みましょう。
例えば・・・
- 週3回の場合:全身法を月・水・金
- 週4回以上の場合:分割法で部位を分ける
といった筋トレの組み方が分かりやすい例です。
こちらの記事を参考にしてください!
頻度の調整のポイントは、体の状態を基準にすること!
筋肉痛が強く残っていたり、疲労感がある場合は、無理に予定通り行わず、休養や軽めの筋トレに切り替えましょう。
セット数で負荷をコントロールする
筋トレで同じ部位を適切な頻度で鍛えるためには、セット数を調整して負荷をコントロールすることも大事です。
頻度だけを意識して同じ部位を筋トレしていると、自分では気づかないうちに回復が追いつかなくなることがあります。
基本となる考え方は、頻度を多くするほど1回あたりの筋トレの負荷を下げるということです。
同じ部位を週1回しか鍛えない場合は、1回のトレーニングでセット数を多めにしてしっかり追い込む方法が向いています。
ですが、週2〜3回鍛える場合は、1回あたりのセット数を抑え、疲労を溜めすぎないことが重要です。
高頻度で行う場合は、限界まで追い込まず、2〜3回余力を残す回数設定にすることで、ケガやオーバートレーニングを防ぎやすくなります。
疲労感や筋肉痛の残り具合を見て微調整することが、同じ部位を長期的に効率よく鍛えるコツです。
筋トレで同じ部位を高頻度で鍛える際の注意点
休養日を必ず確保する
筋トレで同じ部位を効率よく鍛えるためには、休養日を必ず確保しましょう。
筋肉は筋トレ中に成長するのではなく、休養中に強くなります。
休養を取らず同じ部位を高頻度で鍛えた場合、疲労が抜けきらないまま次の筋トレを行うことになり、怪我やオーバートレーニングのリスクも高まります。
基本的には、同じ部位は最低でも48時間程度の回復時間を設けるのが目安です。
筋肉痛が強く残っていたり、疲労感が抜けていない場合は、無理に筋トレをせずに休養を優先しましょう。
しっかり休むことも筋トレの一部と考え、休養日を定期的に組み込むことで、同じ部位を長期的かつ安全に鍛えることができます。
栄養不足にならないようにする
筋トレで同じ部位を高頻度で鍛えていても、栄養面の管理が疎かになると効果が出ません。
栄養が不足していると筋肉は回復・成長できず、効率が悪くなります。
栄養の中で特に重要なのがたんぱく質です!

たんぱく質は意識して摂ろうとしないと不足するものです。
なので、プロテインで足りない分のたんぱく質を補いましょう!
また、エネルギー不足も要注意です。
炭水化物が不足すると、トレーニング中のパフォーマンスが低下し、十分な刺激を筋肉に与えられなくなります。
高頻度トレーニングを行う場合ほど、炭水化物を適切に摂ることが大切です。
さらに、ビタミンやミネラルも回復を支える重要な要素です。
偏った食事にならないよう、バランスの取れた食事を心がけましょう。
痛みや違和感がある時は無理をしない
体のどこかに痛みや、明らかな違和感がある場合は無理をせずに筋トレを休みましょう。
動作中に鋭い痛みが出る、関節に違和感がある、トレーニング後も痛みが引かないといった場合は、体からの危険信号と考えてください。
このサインを無視し続けると、炎症や慢性的な怪我につながる可能性があります。
一時的に休むことを後退と思わず、長期的な筋トレの継続に繋がると考えましょう。

筋トレで同じ部位を高頻度で鍛える際のおすすめアイテム

ほとんどのジムには、マットやチューブ、ベルト、ダンベルは常備してあります。
なので筋トレ初心者が、揃えるべきはパワーグリップとリストラップです。

パワーグリップ
パワーグリップは握力の疲労を抑えることができます。
背中のトレーニングをしていると、背中の筋肉より先に、
握力に限界がきて扱う重量が下がってしまうケースが多いです。
パワーグリップをつけることで、握力の持久力が増し、背中を追い込みやすくなります。

ALLOUTのパワーグリップは安いのに高品質なので、
これから筋トレを始めようとしてる人におすすめです。
リストラップ
リストラップは「ベンチプレス」や「ショルダープレス」の際に、
手首に巻くことで、手首の怪我を防ぐ効果があります。
胸・腕・肩の種目では手首に想像以上の負荷がかかるので、リストラップは必須です。

リストラップもALLOUTが安く、高品質で初心者におすすめです。
まとめ

ベンチプレスで手首が痛くなる原因の多くは、フォームやウォーミングアップの時間、重量設定などの基本的な部分にあります。
筋トレで同じ部位を鍛える際の理想の頻度は目的によって変わります。
自分が何の為に筋トレをするのかを明確にし、正しい頻度とトレーニング方法を継続することが効率的に鍛えることに繋がります。
人それぞれ、目的や筋トレに使える時間は違うので、自分に合ったやり方で筋トレを継続して頑張りましょう。